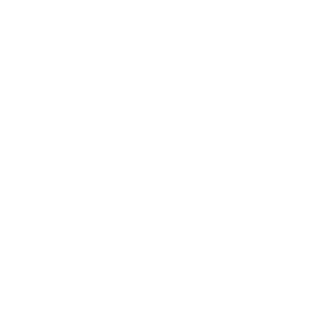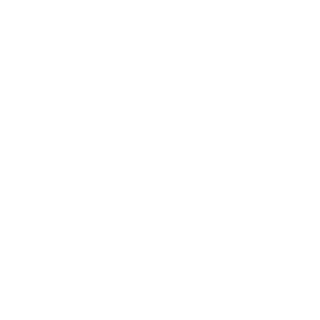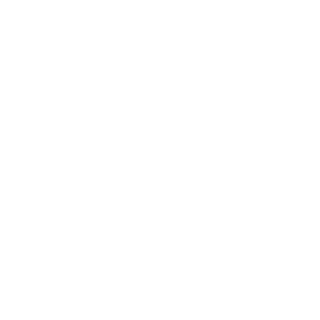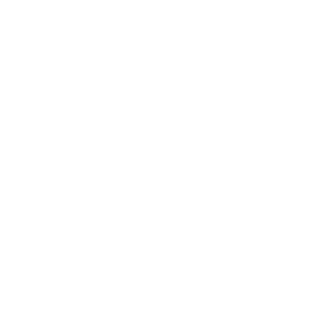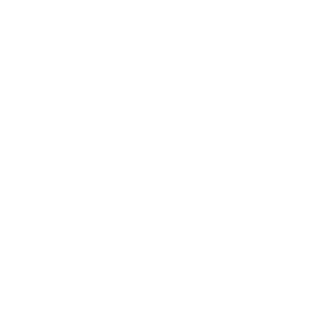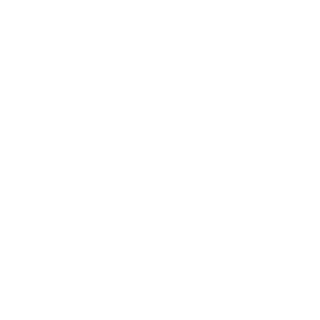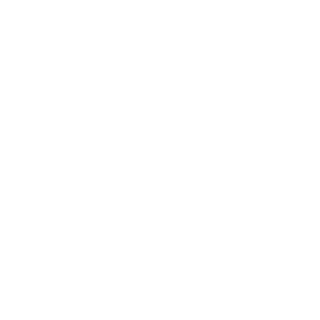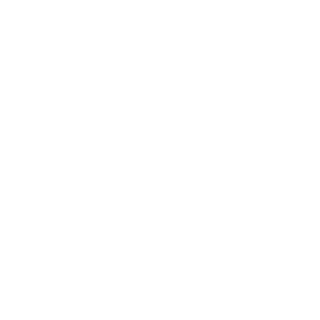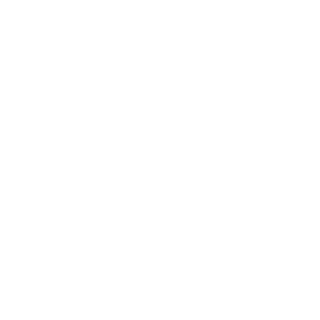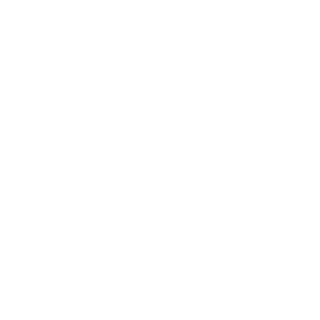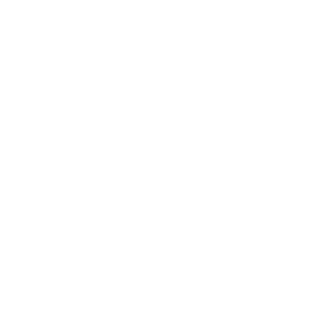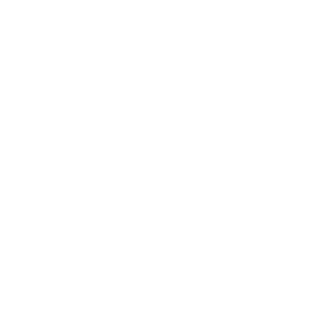

◇

金目鯛と大根の煮付け
◇

2006/04/01と同一の作品
中央は石舞台
◇

借景の彫刻
syhakkei
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
「彼方」
1989年制作。
「彼方とは、今 此処のこと」。
というようなことを考えていました。
境界領域。国境や狭間などについてを思っていました。街ではビルとビルの隙間の空間の展示を考えていたころ。
そそり立つモニュメントのようでは無く、低い平たいものをつくりたかった。
作品を観るのではなく、傍らで弁当を広げたくなるような作品。
当時読んでいた本のなかに、登場するティアというひとが踊る話。※
そういう話と重なった。
石の舞台です。
鉄材は、道。
たいまつが灯され、祭事が執り行われる。
彫刻は上空から見ると羽ばたき飛んでいる鳥の形に成っています。
遠景の山を思いながら、ゆるやかな斜面に配置しました。
背後の森や山には、古墳群があります。
静かで風景の美しい空間。周囲の草も四季折々変化します。
やがて鉄は朽ちて石の配置だけが残るだろう。ということを考えて作りました。奈良で酒石などをその数年まえに観ていたのでそのようなことをイメージしたのかも知れません。
背後の森でパフォーマンス作品「土の香り」を行いました。
写真には写っていませんが、舞台裏手に置いてある石にはアザラシの顔が線彫りしてあります。
その石は、近くを流れる揖保川からの物。石彫シンポジウムの開会式で矢を入れて半分に割った片割れ。
石のもう片方は、道標という別作品にしました。道標には、水を確かめる水槽が付いています。
この作品は、兵庫県播磨新宮、西播磨文化会館に現存します。
最近、グーグルアースで、この作品が確認できたのに驚きました。点のようにしか見えず、知ってる人にしかそれとは解らないと思いますが。
まさかほんとうに空から観れるとは思っていませんでした。
※その本は、ライアル・ワトソン「未知の贈り物」

a chair
◇
椅子は、よくつくるモチーフです。
こまごま小さい作品も含めると、100点以上つくっていると思います。

meet again / for the bereaved family

◇
この建物の内部には温泉があります。
温泉に入る人は、まず側面の階段を上がり、一端内部に入り内部階段を上って再び外壁通路を歩き階段を上って屋上に出て、屋上の縁歩いてさらに外壁階段を下り、正面テラスから内部に入ります。そして内壁階段を下り通路を歩き、ようやく入浴することができます。
四角く切り取られた空が見える温泉です。
入浴後、帰りは、同じ道順をたどります。
長湯でのぼせているので、より足下に注意しながら歩かねば成りません。
テラスや屋上で、風景を眺めたりして休みます。

ceramic bowl
◇
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
私の作品は、だれでも手に入る素材を使用し、だれでも出来る技法でつくろうとしています。
デッサンやドローイングは、一般的な絵の具やら筆やボールペンやノート。街で買える粘土。技法的には「ひねり」と「板つくり」以外はほとんど使っていません。土の焼成方法は、もっとも一般的な焼き方によって作られています。
街の陶芸店で買えるもの。電気窯による酸化焼成。
ですから、窯に入る前の段階までで、作品のほとんどが決定されています。
備前などの伝統陶芸をやってらっしゃる作家の方とも機会がある度に話すのですが、
炎芸術を徹底するためには、「田舎に住んで、登り窯を持つしかない」と常々思います。土を掘って、土をつくって。釉薬をつくって。
話を伺う度に、これは私がいくら電気やガス窯を使って、還元焼成したって、かなわないと思います。
ならば都市部では、土をつかった作品で、なにができるのか。
だれでも手に入る素材、だれでもできる焼き方、だれでも知ってる技法。
それをつかって、自分にしかできない表現を立ち上げることはできないだろうか。
を目指す…。
のだけど、「自分にしかできない」などと言ってしまうとハードルが高いし傲慢かもしれないので「自分らしい」とか言っています。だが、じぶんらしい…というのも、自分から言ってしまうとなんだか曖昧で気持ち悪い言い方。
▽

◇

◇