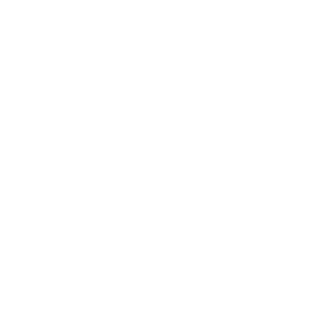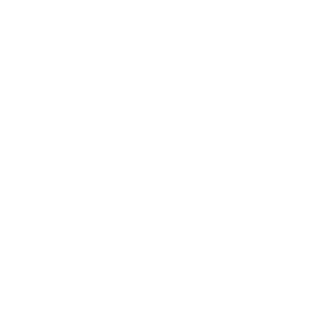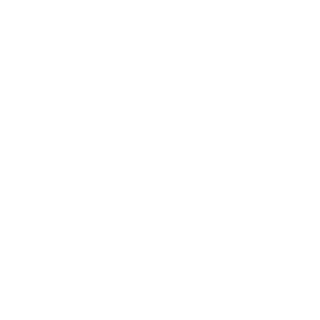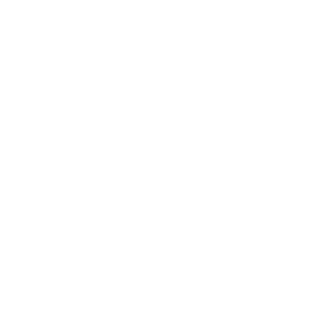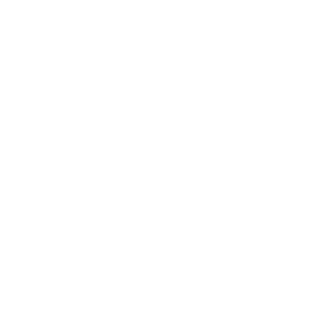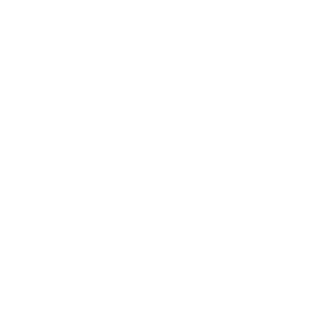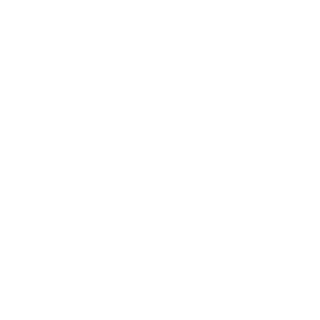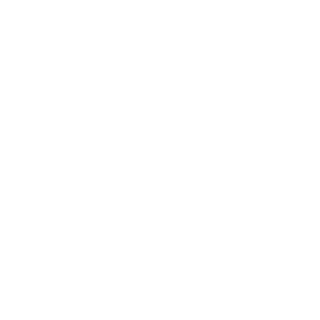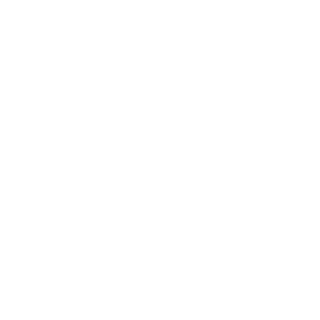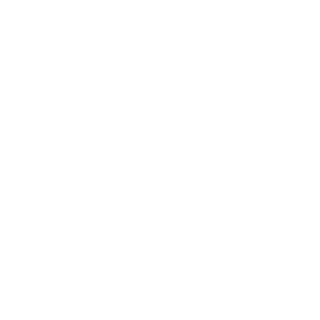それでも あろうとする
『一回性』のところの記憶の集積
思い出そうとする 取り戻そうとする 回復しようとする
それは 二度と起こりえない にもかかわらず あたらしく うまれる 一回性として
とりかえしのつかなさ
◇
柱は海を ささえている
海は この 柱で ささえられている
△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△
ときとして ほんとうにほんとうに 美しくて
ほんとうにほんとうに かわいらしくて 愛しくて
だれのことも 驚かさず 脅威させず
奇抜では 無く
小さく ある
作品は 語らない
手のひらにある 手にあまらない ここにある かけがえのない
必要とするひとのためが 小さく そのひとの手中にある むきあえる 対峙する ここに
そして 小さく 空 小さく 羽ばたいて行ける 小さく いつまでも一緒に みんなで個々に 小さく 静かに 強く 負けない
そういうような リアルな なにかを つくれないものだろうか つくれはしないものだろうか
緒方敏明 作品展
「だれも いない」
2009年11月9日(月)〜 11月30日(月)
場所 cafe gallery SHEEP
大阪市都島区都島本通り3-25-7
電話 06-6925-1003
月曜から金曜 11時30分から19時30分
土曜 9時30分から19時30分
日祝 休業
地下鉄谷町線・都島駅下車・1番出口・東へ徒歩3分
旅について・私は なにも知らない
私は此処が どこなのか知らない
此処が東京だとか大阪だとか和歌山だとか 新宿だとか心斎橋だとか都島だとかいう地名・駅名はわかる
だけど
此処が どこなのだか 知らない いまだ知ったことがない
私は 此処にずっと居るのに「此処」がどこだかわからないまま。
そのことで とても不安になることがある
足下が ふわふわだ 目前が 不確かだ
私は、たとえば大阪駅が地球のどこらへんにあるのかを 知らない まったく感覚的にわからない
私は旅らしい旅をしたことがないから
旅をしないことは距離を知らないこと 時間を知らないこと なんの存在も知らないこと
地球のだいたいのサイズも大陸の幅も知らず 森の時間も大地の速度も知らない
妄想の世界に身を投げ 空想で出逢うのは 自己の分身ばかり
旅人は 此処がどこかを知っている
此処が「世界のどこらへん」なのかを知っている
時のなんたるかを知っている
人が他者であることを知っている
地球を縦に半分くらい歩いたら どのくらい時間がかかるのかを知っている。砂漠をリヤカーをひいて歩く。なんで。想像ではなくて ほんとうにやってしまう。なんでできるのか。わからない。
地球を横に半分くらい走ったら スニーカーの底がどのくらい減るのか そういうことは、もしかしたら知らなくても生きれることかも知れない。一日に100キロ走る快感は知らなくても良いことかも知れない。なんでだ。
でも そのことを体感で知らないということは やっぱり「此処」がどこだか知らないということなんじゃないだろうか
マイナス40度の中をなんで延々歩くのだ。なんで?
大陸の大河を なんでイカダで身を任す。
私は 旅の歓びや達成感も知らないし ほんとうの「へこたれ」も知らない ほんとうにバテたことも無いはずだ
それは やっぱり 「此処」がどこだか知らないということなのだろう 川がどのように流れているかも なにも知らないのだと思う
なんでだ。
わからない。なんでがなんでだかもわからない。なんで 私は「なんで」と思うんだろう。わからん。
私は「私は」 と思うのが めんどくさい。だけど「此処」がどこだかは 知りたいと思う。此処がどこだろうが生きてるんだろうけど。知ることによって意味の探究というのじゃなくて、自分は知ることによって「意味」を断ち切りたいのだと思う。考えまくっていることろから突破したい。とか言っても 知れることは やっぱり たかだか知れてるので でも 意味なんか要らない けど 要る
考えずに 想い感じる連続で 止まらずに静かに 「私は〜」などと言葉にしなくて良くてわからなくてもよくて知っていて触れないけど在るのに見えなくて 意味に追いつかれず 具現化する前の感受性そのものになる
旅人のはなしを 聴きに行こうと思います
地球上のさまざまな定点から 「此処」を 体感することができる人々
◇◇◇◇◇◆◆◆◆◆◇◇◇◇◇
地平線会議30周年記念大集会《躍る大地平線》
期日 2009年11月21日(土)
会場 新宿区牛込簟笥区民ホール
新宿区簟笥町15 電話03-3260-3421(大江戸線「牛込神楽坂」A1出口0分)
開場 12:00 開演 12:30 参加費 1000円
19:30 FINISH
20:30頃から 二次会
居酒屋「竹ちゃん」4階大広間 神楽坂6-38(会場から徒歩5分)
電話 03-5229-6721 会費 3000円(予定) 地平線オークション
地平線会議・公式サイト
毎日新聞 ウェブ記事から
http://mainichi.jp/area/tokyo/news/20091119ddlk13040263000c.html
山岳系雑誌「山と渓谷12月号」で
地平線会議30周年について
8ページの特集が組まれています。地平線会議・366回の全報告会リストも載っています
◇◇◇◇◇21日のプログラム・地平線会議サイトから◇◇◇◇◇◇
12:50 PART1 自然に生きる、野性を食う
松原英俊(鷹匠)+服部文祥(サバイバル登山家)+関野吉晴(グレート・ジャーニー、冒険家、医師)
主体的な「食」を探求する3人の野生児が語る、現代における“動物としてのヒト”の生き方と、その具体的な方法論。
14:00 PART2 縄文号ができるまで
黒潮カヌープロジェクトスタッフ(佐藤洋平、前田次郎)+関野吉晴
縄文的思考法(?)を駆使し、ローテクでいかに海を渡るか?野心的な計画にとりくんだ若者たちは何を見たのか?!
15:00 品行方正楽団 第一部 「パライソ」
長岡竜介(ケーナ)+長岡典子(ピアノ)+白根全(チャンチキ)+大西夏奈子(ボンボ)+車谷建太(三味線)+長野淳子(三線)+張替鷹介(バイオリン)+長野亮之介(太鼓)
地平線通信300回大集会で生れた幻の無国籍音楽バンド、パワーアップして復活!
15:40 PART3 あれから30年−ぼくらの旅の現在地
岡村隆(地平線発起人)+樫田秀樹(ライター)+白根全(カーニバル評論家)+山田淳(山岳ガイド)+広瀬敏通(ホールアース自然学校代表)+青木明美(旅人)
この30年で“地平線的な旅”はどう変化して、今、どうなっているのか?
17:20 PART4 記録すること、続けること
司会:江本嘉伸(地平線代表世話人)+岸本実千代(旅人)
地平線会議発足時からの大テーマ“記録”をめぐるリレートーク!次々と飛びだすゲスト人脈の広さは当日のオ・タ・ノ・シ・ミ
18:40 品行方正楽団 第二部「ミラグロ」
19:20 ダイナミック地平線
地平線オールスターダンサーズ
満を持して放つ、地平線の旅人ダンスチームによるグランドフィナーレダンス!!!
19:30 FINISH
20:30頃から 二次会
居酒屋「竹ちゃん」4階大広間
神楽坂6-38(会場から徒歩5分)
電話 03-5229-6721
会費 3000円(予定)
幹事 大西ジミーカナコ
恒例!地平線オークション ここでやります!一味ちがうお宝オークションです!
地平線報告会は、どなたでも参加していただけるオープンな場です。テレビをはじめとする二次的な情報では決して味わえな い、世界を旅してきた報告者の「生の声」を直接聞くために、1979年9月から毎月欠かさず開催されています。どうぞ気軽に参加してみてください。
展覧会を行います
素晴らしい喫茶店 cafe SHEEP
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
緒方敏明 作品展
「だれも いない」
2009年11月9日(月)〜 11月30日(月)
場所 cafe gallery SHEEP
大阪市都島区都島本通り3-25-7
電話 06-6925-1003
月曜から金曜 11時30分から19時30分
土曜 9時30分から19時30分
日祝 休業
地下鉄・谷町線・都島駅下車1番出口から東へ徒歩3分
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
鬼のシンデレラのはなし
きのうのおには きょうのほとけ
こわいはなしか やさしいはなしか
きょうも かおを ぬぎました
仮面では無い これは顔 さっきまで顔だったけど 脱いだ今は仮面
顔だったときは 怖かった 恐ろしいよ自分 でも自分だからわからない
此処に 鬼のシンデレラの靴がある