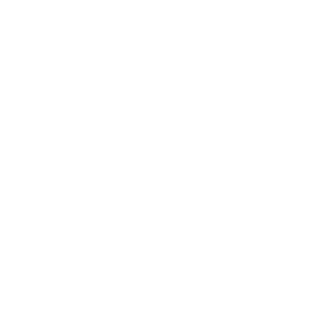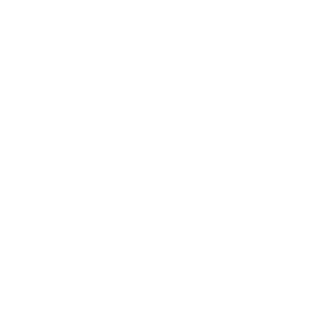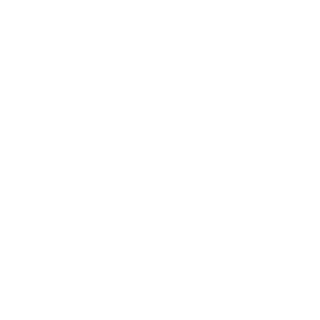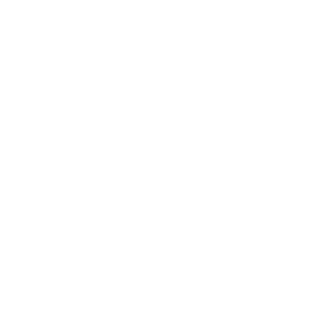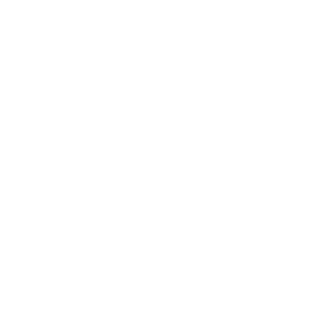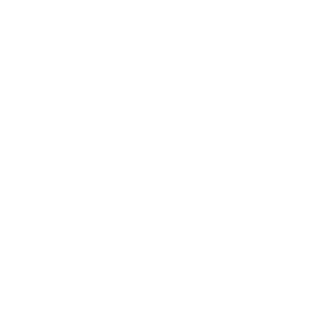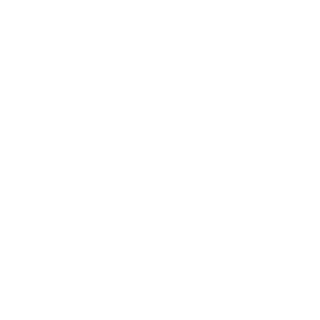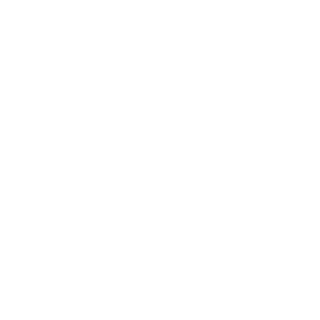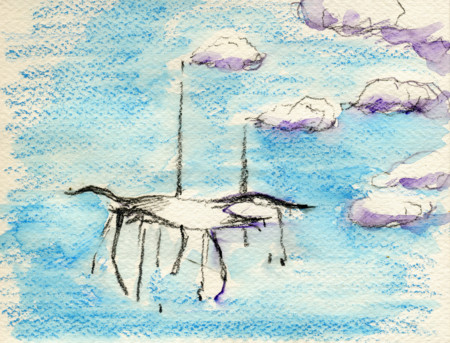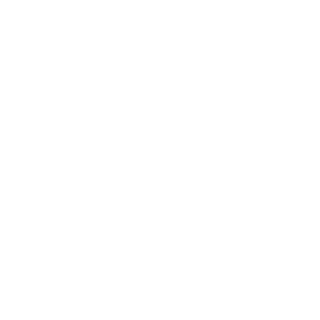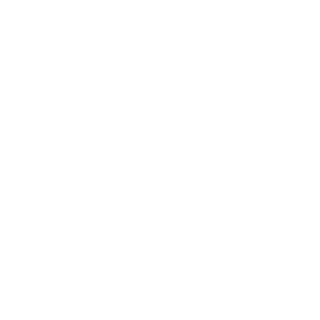儀式に向かう家族
ずんずんずんずん歩く感じ
いい太陽が来たので 空き地でロケハン
この大きさの象 その世界へ はいってゆく
ぼくたちも 小さなロケ隊
太陽光の動きに合わせて いくつかの作品を撮影する
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
緒方敏明 展覧会について
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇緒方敏明 展覧会
「とりの とぶ たかさ」
ancient
会期 9月26日から10月12日まで
休館日 9月30日 10月6日・7日
開館時間 朝11時から 午後6時まで
会場 小野町デパート
和歌山市小野町3-43 西本ビル
電話 073-425-1087
会場の「西本ビル」は、昭和二年築 前の大戦で焼け残った 移築もせず 記念館にも成らず 今も社会生活と現場共存する『現役ビルディング』です。
古いはずなのに新しい気持ち どうか 一度体感してみてください
西本ビル
小野町デパート・ブログ
小野町デパート
http://www.onomachi.jp/main/?page_id=2
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
展覧会をおこないます
以前から想い創っている世界があります 「しろいまち」と いいます
今回は 「しろいまち」の 歴史について考えています
器も その当時から 使われているものを創っています
「いにしえ」というニュアンスの単語が、ほしかったのですが。「ancient」にしました
邦題は「とり の とぶたかさ」です
世界は もしかしたら こうだったかもしれない そのような「想い」に行って その体感をつくっています
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
世の中は風化してゆく出来事で溢れているかもしれない
しかしながら ときとともに輝きを増す記憶は糧となるだろう
素晴らしきことは いつまでも新しい
いつも自らとともにあるから
なにも古いものなどない
石垣も家も
人が住めば家は息をふきかえす
巷では 遅れている人とか 古い人とか言うけれど
遅れているひとはいない 人は古くならない 古いひとなどただのひとりもいない
ひとは傷つく
ひとは老いる
けれども なお人はあたらしい
だれひとり時代遅れにも成らず 老若男女もれることなく だれもがみんなあたらしい
今よりも一秒未来を生きている人も 今よりも一秒過去を生きている人も ただのひとりもいない
ときとしてわたしたちはバラバラに居るように見えるけれど
たった今産まれた赤ん坊も 明日旅立つ老人も
世界中のすべての人が寸分の違いもなくまさに時代の最先端を一緒にいきている
だから 人は いつもあたらしい
あのまちのじかんと 此処の時間はちがうのだろうか
たぶん それぞれのひとには 絶対に壊れないじかんというものがある
海たる海 空たる空 は いま ここにある
記憶をたぐるときに光がやってくる
古からの光に足下を照らされて いまを生きている
もしも 今 失うことがあるとすれば
失ったものをそのままに知ることによって
この記憶を光にして また未来へと投げることはできないものだろうか
人々は 光や水を大切にしてくらしている
村には 光や水にまつわる建物が いたるところにある
子どものころ「この建物の中では お菓子をつくっているのにちがいない」と思っていた
だけど 大人たちと中へ入ると お菓子はいつも片付けられていて そこには無かった
大人は 秘密ばかりだ
大人たちだけで お菓子を食べている
大人は いつもずるい
そこで 子どもたちは 仲間と誘い合わせて 忍び込むことにした
ある満月の夜に
星の降る夜に
そうしたら ほんとうに たくさんのお菓子があったんだ
「やっぱりな」と 勝ち誇ったような気分だった
お腹一杯お菓子を食べた
建物の中は 月の光や星の光で キラキラに満たされていた
そして
「このことは 絶対に絶対に秘密だ」と ぜったいのぜったいのぜったいの約束をして 夜明け前に家へ帰った
◇◇◇◇◇◇◇◇◇
「いまさら…だけど」と 思うのだけど
今 この建物は ほんとうのお菓子工房に成っている
あのとき忍び込んだ仲間が 社長をしているんだ
空からの光が お菓子を特別の味にする
1987年制作の作品 未発表
今回の和歌山展覧会のテーマ(物語)に根元的に繋がる作品だと感じたので 公開することにしました
私にとって とても大切な 意味を持つ作品
◇◇◇◇◇◇◇◇◇
果物を売っています
鶏が居ます
崩壊した建物が あります
詳しい話は 会場にて
俯瞰(空間のスケール感)について 気球に乗れたことは とても参考に成りました (2009年5月)
気球は、「風と同じ速度」で進むので ほとんど風を感じないです
時速100キロで進むときも、時速100キロの風に乗ってるわけだから、理論的には空気抵抗は無いはず。
鳥もグライダーもこういう飛び方はできない。気球だけができる。タンポポの種とかもそうかもしれないけど。
そして バーナーを炊く音以外は まったく音がしないです。静かです。高い樹木の真上に停止したときなど、とても不思議な気持ちになります。あり得ない場所に自分は居る。気球の籠(ゴンドラ)の自分の足のすぐ下に樹木のてっぺんがある。
籠が籐製なのがいい感じです。
さまざまなスケール感を知ることができます。
自身がレンズになったような感じ。いや やっぱり鳥か…
地上50センチでも飛行可能だし、葦の草原をすれすれに進んだり、高度500メートルまで一気に上昇したりできる。前進は風の方向 風の速度だけど、上昇 これが以外に早い。
あっという間に500メートル。
大気の奥行きが違う
目で深呼吸できる感じだ
手を伸ばせば 高度500メートルの空気があるのだ だから実際に高度500メートルの空気を吸えるわけだけど っていうか自分も丸ごと 空中の此処に居るわけで
その「居る」感が 楽しいのだけど
「好奇心」の熱き伝道者・冒険家の安東浩正さんに誘われて。 大感謝です
http://www.youtube.com/watch?v=Jktdzx9tYrI
安東浩正さんの公式HP
http://www.tim.hi-ho.ne.jp/andow/
創作が長丁場に成ってくると 世界観に対して目が慣れてくる
「慣れてくる」のは いいことのようだけど、世界に馴染みすぎると 観察力が低下するような気がする
世界での滞在に心的なゆとりが出来て 好奇心が別のことに移行するのかも知れないけど
逆に 焦りみたいなことも視力(観察力)に影響するのかもしれないです
そういうときは現実に立ち戻って 視力補正をします
なぜならば、想像の世界や 夢の世界を 観察して創るのも やはり「視力」だと思うから
自身が「今、此処」をちゃんと観ることができていれば、夢の世界でも 周囲の事態を把握できるはずだと思うから
想像の世界では 「わからないことはわからない」。意味不明の形や色に変換できそうもない意識がそこらじゅうにある。と言うか、妄想の風景は欠落部分だらけ で当然だと思う。だから、「わからないところはわからない」ように創ることが 重要なことに成ってくる。
しかし、そこで視力が低下してしまっていると わかってることとわかっていないことの判別がつきにくくなって わからないことを あたかも「わかっているかのように」勝手につくってしまう。そうすると 作品がチープになってしまう(狙わずにです)。そうなるとそれは想像の描写ではなくなってしまう。
【創作】とは『想像の描写』であると思う。
想いの中に「見えてることを そのままに」創ればいい。
だから、いくら興味深い初めての世界へ行って おもしろそうな想像をしていたとしても「視力」が鈍っていたのでは 表現できない
調整の為には
現実界の身近なものをつくってみる
なるべく ありきたりなもの、一般的に手に入るもの。知っているものが良い。そのほうが 自身の現時点での「まなざし」の性能を把握できるから
この方法は、自分では効果があると思っています。特に知らない事柄 観たことのないものを想像して創るときに威力を発揮します。たとえば象を想像でつくるとかもそうです。私はわからないところはつくれませんから。デフォルメから不自然な作為を排除してゆける。そうすることによって 実際現実とは違うけど 「まさに在る」ような作品をつくることが可能になってくるのだろうと 考えています。
だから現実描写のモチーフは奇抜なものではなく「ありきたり」「身近なもの」ということが大切。見慣れたものに新鮮な発見を見つけてゆくこと。
私は、練習はとても嫌いなので 楽しく興味津々で 本気本番としておこないます 好奇心と共に
一個の「おくら」に集中する。片口イワシは、今の調整にはベストだと感じたので買った(固体内の色バランスで全体感を現す為には適材)。ピーマンは前回の視力調整のときの作。
自己注意点としては
この作業は、視力維持の為の 現実視界への帰還のための 私自身の現時点での「方法論」でしかないということ
それは、制限があってかなり閉塞したものであるということ
そのことを ぼく自身が注意すること
つまり 目指しているのは、このような意味の「そっくりさん」的リアリティでは無い
だから こういう作業自体が「焦り」を生む可能性もある それでは本末転倒してしまう
『たしかな「まなざし」』は大切だとおもうけど 見える通りにつくれる必要は、創作(芸術)については どこにもない。
それよりも「想いの姿を みたままに創る」ことなのだと思います。
ここが、 ジャーナリストとの現実的な差異かも知れない
いったんベースキャンプ(宿)に戻って 心身落ち着くみたいな
今 完全に 創作の世界から意識の手を引いてしまうと 今度は世界にすら行けなくなる 今は、それは困る。だから 現実界のいわゆる「気晴らし」みたいな遊びに没入するのではなく 近隣近似のことで 調整をはかる
目が 慣れてきても
いま 焦ってはいけない
此処まで来たんだ 調整すれば 取り戻せる
そこから また歩く
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
昔の石垣も 言葉がある
家具や柱は 憶えている
石垣の積み石が ひとつ失われるたびに ひとは記憶を失う
憶えておこう
ただ 今の この目の感覚を記憶の網膜に焼き付けておこう
それでもぼくは忘れる
多くは忘れるけれども 古びない記憶が必ずある
それを体内で見極め 造形変換して作品としてアウトプットする
…できれば それができれば
だが 先を急いでは いけない
焦らないこと
今だ 今しかない
と
焦るごとに
石垣が またひとつポロリポロリと 崩れてゆく
「かけがえのないもの」は 金では買えない
物も街も道も社会も川も海も山も空も自由も安心安楽も遊び場も なにもかも金で買い取られてしまう
そして 彫刻家橋本平八には、絶対に成れない 生き方も真似できない
どうしよう…
だけど、だけど、だからと言って、なんら怯むことはないのではないか。世界は いまもなおのこと「かけがえのないもので満ちあふれている」ではないか。
自分は どこのどこを、なにのなにをみているのかということ。
大金持ちが世界の全てを買い尽くしたとしても 「かけがえのないもの」は買えはしない
かけがえのない意志 かけがえのない想い かけがえのない旅
光 水 重力 とき けはい とまらないもの 触れないもの みえないものの多くは「かけがえのないもの」
世界のなかで「かけがえのないもの」だけが 人々のものだ
そしてだれもが ここへの横暴な侵害をゆるしてはならない
「かけがえのないもの」を死守するのだ
いや 守らずとも「確かに在る」ことをしめしつづければいいわけだ
ここは 招き会うところ わかちあうところ
かけがえのない世界に行くと 泉は 枯れることなく 無限に沸いているのだし
世界へ解き放たれている 鳥たちは
そうだ 世界へと解き放たれた鳥たちこそが 今 ここを創るのだ
「空を創る」などと書くと 大仰かもしれないけれど
丈夫な体と 飛ぶ意志があっても
「空」が 無ければ だれも飛べない
だから
空をつくる「何か」が 世界には 居る
空は太古から ずっとあるから
鳥がうまれるまえから 居たのかもしれない
だけど 空が狭くなったから どこからか 来たのかもしれない
空の大きさは かわらない
今朝 みたときは 雲を吐きだしていた
◇◇◇◇◇◇◇◇◇
この作品は 久しぶりに鉄を溶接して創りました
尊敬する彫刻家の好意によって 成すことができました 感謝
◇◇◇◇◇◇◇◇◇
ひとが ほんとうにおもっていることは、日々の仕事が締め切りに間に合うかどうかとか 契約とか利潤効率とかのことなんかじゃ無い 今日という一日に体裁を付けてなんとかやり過ごすことでは無い
ひとは 利害や損得や金銭や勝敗のことを考えて日々過ごしているのではない
ひとが ほんとうにおもっていること ほんとうにやりたいこと 目指していることは そういうことではない
自身の想いのそのまた下層にある想いのまた さらに深いところに それはある
じぶんが ほんとうに おもっていること
ラスコー洞窟に絵を描いたころから途切れることなく生きてきた太古の遺伝子に到達する
アートが生まれるずっとまえからの「絵を描きたい」という想い
◇◇◇
だれのこころの奥底にも 昏々と泉湧く光り輝く懐かしの故郷がきっと在るにちがいない
シャングリラに咲く あのはなを 手のひらに納め 此処へもどってくる